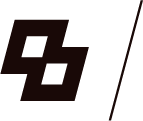コンチネンタルの新しいスポーツタイヤ「ContiSportContact5」をレーシングドライバー/モータージャーナリストの桂伸一氏が試乗。その実力は?
コンチネンタルの新しいスポーツタイヤ「ContiSportContact5」をレーシングドライバー/モータージャーナリストの桂伸一氏が試乗。その実力は?
 コンチはここ数年、精力的に新商品の発表と試乗会を開催している。昨年はストリート用としては驚愕のグリップ性能を誇るContiSportContact5P(CSC5P=コンチ・スポーツコンタクト5P)だった。今年はそのCSC5Pと基本コンセプトを同じくする新世代のスポーツタイヤ「ContiSportContact5(CSC5=コンチ・スポーツコンタクト5)」である。
コンチはここ数年、精力的に新商品の発表と試乗会を開催している。昨年はストリート用としては驚愕のグリップ性能を誇るContiSportContact5P(CSC5P=コンチ・スポーツコンタクト5P)だった。今年はそのCSC5Pと基本コンセプトを同じくする新世代のスポーツタイヤ「ContiSportContact5(CSC5=コンチ・スポーツコンタクト5)」である。そして、さらに新世代のエコタイヤ「ContiEcoContact(CEC5=コンチ・エココンタクト5)」も同時発表。試乗会も同様に開催されたが、従来のCSC2やCSC3のユーザーが多い1to8.netでは、CSC5の話題をお送りする。 ちなみに、CSC3から4をとばしてCSC5を名乗る理由は、"4"を敬遠するアジア圏に配慮したからだという。
コンチネンタルの国際試乗会に向かった先は、ポルトガル・ファーロからほど近い「アルガルヴェ・インターナショナルサーキット」。 テストコースの「アルガルヴェ」はF1のテストから新旧GTレースまで開催される1周4.7キロ、山の地形を使った高低差の激しいレイアウト。ブラインドコーナーは、通常は左右の先が見えないものだが、ここは"上下"が見えない! 勢い良く駆け下りたらスロー走行車がいてドキッ!とさせられたこともあった。
試乗車はゴルフGTIやアウディTT-RS、ほかにもCSC2やCSC3を純正装着していたとおぼしきモデルたちだ。
驚きはコンチネンタルの太っ腹度合。カーメーカーの試乗会であれば、コースのいたるところにパイロンが立てられ、走行ラインの指示や減速を促すためにインストラクターが同乗したり、ペースカーが先導するのがあたりまえ。しかも、ESPなど、車輌安定装置には触れさせないのが常である。
ところが、コンチは「ご自由にどーぞ!」 おかげで、全開に継ぐ全開で攻め立て、発熱によってタイヤのグリップ力が変化するのか否かまで探ることができた。
メルセデス・ベンツSLSに装着されて登場したCSC5Pは、公道がサーキットになったかと思うほど、強烈なグリップ力で乗る者を魅了した。特に横G、コーナーのグリップ限界の高さで、S字コーナーが連続すると、頭がクラクラするほどのGフォース。首にも体にも強いストレスが加わる経験を、ロードカーではした覚えがない。
一方CSC5は、サーキットで通用するパフォーマンスを、オンロードに適した乗り味や低転がり、耐摩耗性等々に置き換えたといえばわかりやすい。CSC5は、ともかく路面を丸く捉えている。角ばった硬さなど微塵もなく、滑らかに接地している。

しかもグリップ力は高いのに、路面との抵抗感がなく軽快に流れるように進む勢いは、スポーツタイヤにこそ転がり抵抗軽減による走るための速さが必要なのだと感じさせられる。
通常、直進状態からステアリングを切り込むと、タイヤと路面の関係から接地面が変化して手応えに乗り越え感があるのだが、その段付き感というべき現象がこのタイヤにはない。直進から旋回への移行がステアリングを通してシームレスに滑らかにつながる。ニュートラル付近に過敏に応答する領域がない。これはまさにドイツ・アウトバーンでの超高速走行に際して轍や舗装の剥がれ等、外乱を受けた際の安定性に有効だろう。
アルガルヴェのストレートは最速でも210km/hだが、車種や駆動方式に関わらず高速直進に気を使う必要はない。Wレーンチェンジのように急激な動作を起こしても、グリップ力に勝るCSC5は瞬時に安定姿勢を取り戻す。ステア操作初期にクイックな応答性は特に感じられない。それはタイヤの特性があくまでも自然な変化を生むようにつくられているからで、要はドライバーの操作に委ねられる。
つまりクイックに姿勢を変化させたいのなら、ステア操作する速度の強弱でいかようにもできるという意味だ。CSC5のタイヤ形状、ラウンドショルダーが関係して、コーナリング中も路面を包み込むように広い接地面で捉えている感覚だ。
CSC5Pと同様CSC5も、旋回時のアウト側ブロックにGが加わると、ブロックは前後方向にソフトに変形して溝を塞ぎ、ブロック同士が一体化することで、接地面積を拡大する。コーナーで果敢に攻め込んでも、まずスキール音を発さないグリップ限界の高さの秘密はここにもある。
スポーツタイヤとしてのキビキビ感よりも、操作に対する忠実な動きを重視したCSC5は、欧州メーカー9社に納入される。もしも、次期愛車にCSC5が装着されていたら、それはとてもラッキーだと思う。
(Text by Shin-ichi Katsura)